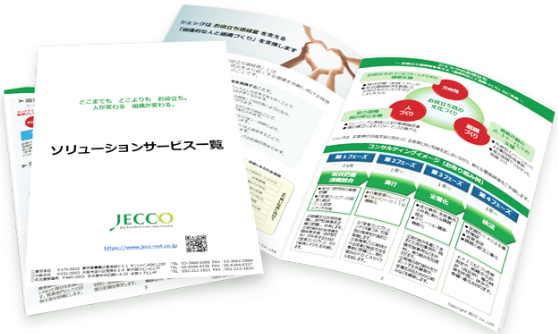この時期に問われる育成力と関係性の質〜若手が辞めない組織の共通点〜
新年度が始まり、現場では新人の受け入れやチーム体制の調整で慌ただしい日々が続いたことでしょう。6・7月になると、組織は「一段落した」ように見えるかもしれません。
しかし、実はこの「一段落」の裏で、小さな違和感や不安、孤独感が蓄積しやすい時期でもあります。職場のリアルな姿や仕事の現実が見え始め、「このままでいいのだろうか」と悩む声も出てきます。
このタイミングこそ、新人・若手社員の「転職検討」が出やすい時期であり、マネジャーの育成力・関係構築力が試されるタイミングでもあるのです。
マネジャーが直面する3つの “育成のズレ” とは?
この時期、現場のマネジャーからよく聞かれる声があります。
① 指導しているつもりが、若手には伝わっていない
「ちゃんと説明したのに、理解されていない」「注意したら、次の日から黙ってしまった」
➡このようなすれ違いは、認知のズレと信頼関係の薄さが背景にあります。
② モチベーションを引き出すつもりが逆効果に
「やる気を出してほしくて厳しめに伝えた」「励ましたつもりがプレッシャーと受け取られた」
➡Z世代の若手は、“上司の言葉の真意”より“安心して話せる関係性”を重視しています。
③ 対話しているつもりが、実は“報連相”だけ
「毎週1on1をやっているけれど、業務報告で終わっている」「本音を話してもらえない」。
➡対話の頻度ではなく、“対話の質”が信頼と定着を左右します。
若手が辞めずに育つ組織の共通点
退職理由として「やりがいがない」「成長を感じられない」「人間関係に不安がある」といった声はよく挙げられます。
しかし、辞めない組織には“見えない共通点”があります。
それは、次の3つが組織文化として定着していることです。
■心理的安全性:どんな話題でも安心して話せる土壌がある
■成長実感:小さな成功体験を積み重ね、フィードバックが機能している
■関係性の深さ:自分を「理解しよう」とする上司や先輩がいる
「この職場で自分は大切にされている」「ちゃんと見てくれている」というような実感がある若手は、多少の困難があっても、すぐに辞める選択をしません。
いま、マネジャーに求められる3つの行動
では、どうすればそうした職場をつくれるのでしょうか。
組織文化を変えるには時間がかかりますが、マネジャーの行動から始められる3つのアクションがあります。
観察と内省をセットにする
「最近、○○さんの表情が少し暗いかも」「リアクションが変わったな」―こうした変化に気づくには、観察力と内省の習慣が鍵となります。
忙しい中でも、一人ひとりに意識を向ける姿勢が信頼につながります。
対話の質を高める1on1
報告・相談の域を超えて、「最近どんなことが気になっているか」「何ができるようになったと感じるか」といった、感情や価値観に届く問いかけが、内省と成長のきっかけになります。
支援型マネジメントへのシフト
「指示する」よりも「支える」スタンスへ。自らのマネジメントスタイルを定期的に問い直し、支援者としてどうあるべきかを振り返ることで、メンバーの主体性も引き出されます。
組織文化は、マネジャーの変容から始まる
若手が辞めない組織をつくるには、特別な施策よりも、日々の育成と対話のあり方を変えることが近道です。
現場で最もメンバーに影響を与えるのは、他でもないマネジャーの存在です。
マネジャー自身が変わることで、チームが変わり、やがて組織文化も変わっていきます。
今のタイミングだからこそ、チームと向き合う一歩を踏み出してみませんか?