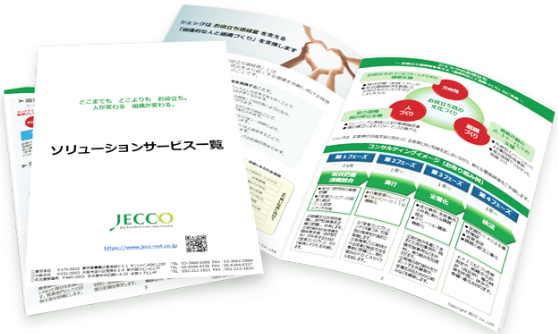営業・アフターサービス部門間の壁をなくす~部門間連携のマネジメント
顧客の購買行動が大きく変化し、サービスや体験の質そのものが選ばれる理由になる時代です。「売って終わり」ではなく、「売った後の体験や成果」をどうスムーズにつなげていけるかが、企業の競争力を左右する要素になってきています。
営業とアフターサービスの連携はさらに重要性を増しています。
その重要性を理解していても、現場担当者や現場マネジャーからは「そうは言っても」という声が少なくありません。営業は受注に、アフターサービス部門はトラブル対応に日々追われ、KPIも時間軸も異なる中で、単なる掛け声だけでは連携は生まれにくいいのが現実です。
“顧客起点の共通言語”で壁をなくす
部門間連携の鍵は、「顧客起点での共通言語」を日常に組み込むことです。現場レベルで実現可能な連携のポイントは、以下のような取り組みにあります。
🔹 引継ぎ情報の「質」を変える
・受注時に営業が把握した「顧客の期待値」や「背景・意図」を、定型フォーマットではなく“温度感”を含めてアフターサービス部門と共有する。顧客が本当に求めていることをサービス側が理解できるようにする。
🔹 現場の声を「循環させる」仕組み
・アフターサービス部門が得たお客様現場のリアルなフィードバックを営業部門に伝え、次の提案やクロスセルのヒントにつなげるために、月1回のフィードバック共有会などの仕組みをつくる。
・業務都合でミーティングに参加できなくても情報が共有できるフォローの仕組みも重要だが、担当者が「できれば参加しよう」「この情報は共有しておきたい」と自然と思うようにするためには、情報共有の結果がそれぞれの部門にとって「役に立った」「受注につながった」などの報告もしっかりと行いミーティングを形骸化させない(忙しいのに参加したくないと思わせない)ことが重要。
🔹 小さな連携を積み重ねられる場づくり
・朝会で気軽に話せるなど、日常業務の中につながりを生む動線を組み込み、部門間の壁を感じにくくする。情報共有(お客様情報・部門の重点方針など)が当たり前になるためには、「軽くて続く場づくり」がポイントとなる。
マネジャーの視点を変えることが連携の要
連携を現場で支えるのはマネジャーの役割です。現場マネジャーには、次のような意識と評価の転換することが求められます。
🔹 マネジャーの意識を変える
・「自部門を守るリーダー」から、「顧客体験全体をつなぐハブ」へ。
・自部門最適ではなく、全体最適を考えるチームリーダーとしての自覚を持つ。
🔹 評価・目標設定の見直し
・縦割りKPIだけでなく、「部門横断での連携行動」や「他部門との協働の成果」も目標として設定する。
<例)以下のような仕掛けが効果的 >
➤他部門と連携してCX(顧客体験)向上に寄与した事例の共有・表彰
➤チーム横断での学び合いの場(相互レビュー・他部署への1日留学など)
“文化”が変われば、組織は変わる
部門間連携が取れないのは、構造よりも“日々の習慣・当たり前”によることが多いようです。だからこそ、その当たり前を変えていく必要があります。まずは前段のような日々の連携を仕組み化していくことは有効です。
仕組み化されたことを実践していくうちに「お客様が喜んでくれた」「リプレイスにつながった」など成果につながれば、 個人の意識が変わってきます。
意識が変われば、「(仕組みでやらないといけないから)仕方なくやる」ではなく、「部門を越えて協力することこそがお客様や自社のためである」という当たり前となるでしょう。組織にその意識や行動が根付いていくと、それが組織の文化として定着します。
お客様から見れば、営業もアフターサービスも関係なく「一つの会社」です。その視点を意識することが当たり前になれば、部門を超えて“共に価値を届ける/新たな価値を創造する組織”となることができます。このような組織変革がいま求められています。