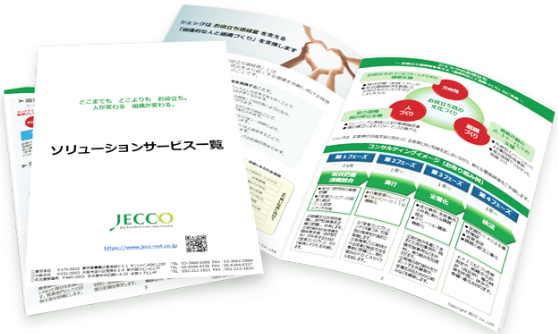プロジェクトが人を育てる~次世代リーダーとプロデュース力を磨く仕掛け
なぜ今、「プロデュース力」なのか?
変化が当たり前となった今、企業の持続的な成長に欠かせないのは、「価値を生み出す力を持った人材」の存在です。与えられた業務を正確にこなすだけでは、新しい価値を創出することはできません。
必要とされているのは、目的から逆算して構想を描き形にし、 部門や立場の枠を越えて人を巻き込み、実行段階で生じる課題を解決しながら目標達成まで導く力です。この能力をプロデュース力と呼びます。
このような力を持つ人材は、問題解決だけでなく、組織に新しい視点をもたらし、部門間連携やイノベーションの推進役にもなり得ます。ですが、こうした力は座学だけでは身につきません。経験を通じた学びと、それを言語化して内省する機会があってはじめて、プロデュース力は育まれていくのです。
「プロジェクト経験」が人を変える理由
私たちが数多くの企業支援の現場で感じるのは、「プロジェクトを経験することで、人は確かに変わる」という事実です。
例えば、ある企業では、若手社員に新しい社内サービスの企画を任せたところ、それまで指示待ちの傾向が強かった社員が、周囲と積極的に対話を重ね、他部署と交渉し、最終的には提案を実現させるまでに成長しました。
きっかけは「誰かが決めたことをやる」のではなく、「自分が起点となって動く」体験でした。
プロジェクトには正解がありません。状況が刻々と変わる中で、「何をするべきか」を自ら問い、「どう進めるか」を自分で考え抜かなければなりません。しかも、他部署や外部との調整も必要です。
こうした“日常業務の外側”にある経験こそが、視野を広げ、行動や思考をアップデートさせるのです。
「育つ」プロジェクト設計の3つのポイント
とはいえ、ただプロジェクトを経験させればよいわけではありません。
「人が育つプロジェクト」には、いくつかの共通点があります。
① 任せるだけでなく、支える
目的や期待される役割を明確にしないまま丸投げしてしまうと、経験は「ただ大変だった」で終わってしまいます。最初にプロジェクトの意義やゴールを丁寧に共有し、必要な支援体制を整えておくことが不可欠です。
② フィードバックと対話の設計
プロジェクトの途中や終了時に、定期的な振り返りや対話の場を設けることが重要です。メンターや上司が「どんな視点で考えたのか」「何に悩んだのか」を丁寧に聞き出し、言語化を支援することで、経験は“学び”へと昇華されます。
③ 成果ではなく「姿勢」と「変化」を認める評価
プロジェクトの結果も大切ですが、それ以上に注目すべきは、挑戦する姿勢や周囲との関係構築の変化です。こうした内面的な成長に気づき、承認することで、次の挑戦への意欲につながります。
次世代リーダー育成のために今できること
プロジェクトは、次世代リーダーを育てる「実践の場」です。そしてそれは、選抜された一部の人材だけでなく、多くの社員が経験すべきものです。
なぜなら、プロジェクトを通じてこそ、「自分の仕事が組織全体にどうつながるのか」を実感でき、視野の広いリーダーが育つからです。
育成部門は、プロジェクトを「学びの場」として設計する視点を持ち、経営層は、挑戦できる環境や失敗への寛容さを組織文化として支える役割を担います。
そして、現場マネジャーは、日々の業務の中に成長のきっかけを見出し、後押しする存在です。
御社では、プロジェクトが人を育てる仕組みが機能していますか?
挑戦の場をどう設計しどう活かすか。そこに次世代リーダー育成の未来があります。