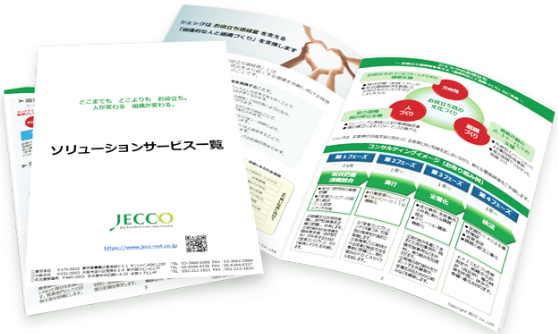AI時代に必要とされる人材とは─変化に取り残されない組織づくりのカギ
AI時代の本格到来と、変わる人材の価値
「AIに仕事を奪われるのではないか」。そんな不安が、かつては一部の人の話題に過ぎなかった時代がありました。
しかし、生成AIの登場により、その懸念は現実味を帯びてきました。特に2022年末に登場したChatGPTは、その対話能力や文章生成の精度によって、知的労働の在り方を根底から問い直す存在となっています。
実際、ゴールドマン・サックスの試算(2023年)によれば、世界中で3億人の雇用がAIの影響を受ける可能性があるといいます。これは決して一部のIT職種に限られた話ではなく、営業、企画、総務、教育といった幅広い業務領域に関わる問題です。
では、こうした変化のなかで「価値ある人材」とはどのような人物なのでしょうか?
そして、企業としてどのように育成し、活かしていくべきなのでしょうか?
本コラムでは、AI時代において「必要とされる人材」と「そうでない人材」の違いを明らかにし、経営・人事・育成の観点から今取り組むべき打ち手をご紹介します。
AI時代に必要とされる人材 vs 取り残される人材
必要とされる人材の特徴
AI時代において価値が高まるのは、「AIにはできない仕事」を担える人材です。たとえば次のような特徴が挙げられます。
・目的や意味を問い、課題を再定義できる
・他者と共創し、関係性の中で新たな価値を生み出せる
・変化を拒まず、学び続けるスタンスを持っている
こうした力は、OECDの提唱する「ラーニング・コンパス2030」でも重要視されており、知識の詰め込みではなく「思考」「行動」「責任」を自律的に選択する力が、今後の教育と育成の中心になるとされています。
取り残される人材の特徴
一方で、以下のような傾向を持つ人材は、AIに代替される可能性が高まり、組織における価値が相対的に下がっていくリスクがあります。
・指示待ち、正解依存の姿勢
・目的を考えず、手段や作業に終始している
・AIを「脅威」と捉え、学習や活用から距離を取る
従来の経験や勘、既存の枠組みにしがみついているだけでは、変化に対応できず、本人だけでなく組織全体の成長を妨げることにもつながります。
経営者・人事・管理職が押さえておくべき育成の視点
こうした変化の中で、育成に関わる立場の人が押さえるべきポイントは以下の3点です。
視点①:「問いを立てる力」を育む
AIは、与えられた問いに対しては高速・高精度で答えを返すことができますが、「そもそも何を問うべきか?」という領域ではまだ不十分です。
今後は、業務の中に問いを立てられる力(クリティカルシンキング・システム思考)がより重要になります。
1on1やフィードバック面談の場を、単なる進捗確認にせず、「なぜそれをやるのか?」「他のやり方は?」といった問いを共有する機会に変えることが、第一歩です。
※問いを立てる力とは
解決しようとする課題を見つけ出す力のことです。
問いを立てることで、解決すべき課題や、考えるポイントを明確にしながら思考をスタートさせることができます。問いを立てることは、思考のスタート地点に立つようなもので、解決したい課題に向かって、その問いに答えようと探究活動が始まります。
このような問いを立てる力には、着眼力、洞察力、批判的思考力(クリティカルシンキング)、創造力、構想力などの力が必要であり、新たな価値を生み出す力でもあります。
※出典:問いを立てる力とは?意味やその力を高める方法、児童生徒への対応ポイントを解説
https://www.asahi.com/sensei-connect/articles/15642471 (2025/6/2)
視点②:AIと共に働くリテラシーを高める
「AIを使いこなせる人材」ではなく、「AIと共に価値を出せる人材」を育てるには、全社員のリテラシー向上が不可欠です。
たとえば、
・AIツールのリスク、限界、活用例を学ぶワークショップ
・各部門での「AIで代替できる業務」の洗い出し
・社内報や勉強会による活用事例の共有
などです。
組織内の知識格差を放置せず、「学び合う場」を設けることで変化への心理的安全性も高まります。
視点③:内発的動機を引き出す支援
変化に適応するには、「自らの意味づけと成長への意欲」が求められます。キャリア自律やミッションの明確化を通じて、社員自身が変化の担い手となる土壌を育てることが、人材育成の本質です。
実践につなげる:打ち手・アクション例
では、明日から現場で何を始めるべきでしょうか?
以下に、経営・人事・育成の各立場で取り組めるアクションを紹介します。
◉ 経営・人事部門のアクション例
・「AI時代に期待する人材像」の定義をアップデートする
・評価制度を見直し、「変化対応力」や「共創性」を反映させる
・全社でのAI活用、リテラシー研修を企画/主導する
◉ マネジャーのアクション例
・1on1で「今の仕事の意味」や「他のアプローチ」を一緒に考える
・ChatGPT等を使った業務効率化アイデアを部内で共有する
・「変化を恐れず学び続ける姿」を自ら体現する
◉ 人材育成・組織開発担当のアクション例
・問いを立てる力を育むワークショップ(例:リフレクション研修、デザイン思考)
・AIと共に働く力を学ぶ「学習する組織」づくり(ピア・ラーニングなど)
・内発的動機を支援するキャリア支援・対話設計
人間らしさが問われる時代に
AIはあらゆる情報を分析し、最適解を高速で導き出してくれます。
しかし、何を問うか、何に意味を見出すか、誰とどんな未来をつくりたいのかといった、人間ならではの営みは、依然として不可欠です。
経営や組織が、この「人間らしさ」に目を向け、育み、活かしていくこと。それが、AI時代においても、社会から選ばれ続ける企業となるための本質ではないでしょうか。
【参考・引用情報】
Goldman Sachs Research「The Potentially Large Effects of Artificial Intelligence on Economic Growth」(2023年)
OECD「Learning Compass 2030」(https://www.oecd.org/education/2030-project/)
経済産業省「人材版伊藤レポート2.0」(2022年)