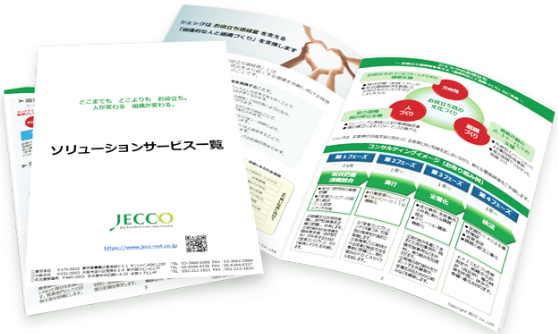上司と部下の信頼関係づくり4段階 第4回:パートナー促進 ~「敬遠感」を乗り越え、信頼を深める段階
「パートナー促進」とはどんな段階か
第1段階の「関係促進」で、人間関係が築かれ、距離が縮まった上司と部下。
第2段階「納得促進」では、方針や判断の背景が共有され、「この上司についていこう」という理解が深まりました。
しかし、ここで一つの転換点を迎えます。
上司の力量が見えてくるほどに、部下の中には「自分とはレベルが違う」「もう相談しづらい」といった敬遠感が生まれることがあります。
それが進むと、上司への信頼や尊敬が、むしろ「遠い存在」へと変わってしまいます。
この段階で必要なのは、「上司と部下が心強いパートナー同士である」という感覚を再び取り戻すことです。
つまり、敬遠感を払拭し、敬愛へと転化する段階が「パートナー促進」です。
「信頼」を失う落とし穴
この段階の最大のリスクは、「信頼を失う」ことです。
敬遠感が生まれると、上司は無意識のうちに部下の“できない部分”ばかりに目が向きやすくなります。
「ここを直せばもっと伸びる」という意図でも、指摘や助言が続くと、部下は「自分は責められている」「否定されている」と感じがちです。
公平さを重んじすぎて“全員同じ対応”にしてしまったり、金銭や地位といった外発的な動機付けに偏るのも注意が必要です。
また、「楽しもう」「やりがいを感じよう」と善意で声をかけたとしても、受け取る側が「上から目線」と感じてしまえば、かえって距離は広がってしまいます。
この段階では、「何が感情的な距離を近づけるか」を判断する力が上司に求められます。
感情を近づける意味
感情を近づける理由はシンプルです。
それは、「モラール(やる気)」が感情によって左右されるからです。
モラールが高い人は、「言われた以上のことをやる」人です。
たとえば営業現場で「もう一件行ってみよう」と思えるのも、製造現場で「もう一度確認しておこう」と思えるのも、上司と部下の信頼関係があるからこそです。
上司を「信頼している」「この人と働きたい」と感じている部下ほど、自然とプラスαの行動を取ります。
このプラスαが積み重なることで、組織全体のモラールが上がり、成果と安心感の両立が生まれていくのです。
上司の打ち手:心服感をつくる
パートナー促進の鍵は、「高次欲求への働きかけ」です。
単に成果や報酬を求めるのではなく、「自分の成長がチームの役に立つ」「一緒に目標を達成したい」という内発的動機を引き出すような関わりが求められます。
1.集団指導は公平原則で、個別指導はタイプ別原則で
チーム全体に伝えるときは一貫性と公平性を意識しつつ、個別で話すときは、相手のタイプに合わせた関わり方を意識しましょう。
2.部下の強みに共感し、肯定する
強みを発見し、共感し、成果につなげることで、部下の自信は回復し、上司に対して“感情的な好意”が生まれます。
3.自由度を広げ、自己責任を促す
やるべきことを細かく管理するよりも、部下に一定の裁量を委ね、「自分で考えて行動する」機会を与えましょう。
上司の信頼を感じることで、部下は主体的に行動し、自らの判断に責任を持つようになります。
4.困ったときには断固として守る
部下が壁にぶつかったとき、上司がその努力や意図を理解し、きちんと支えること。
たとえ結果が思わしくなくても、「あなたの挑戦を評価している」と伝える姿勢が、部下の信頼と安心感を深めます。
5.共通目標の達成に向け、共に動く
上司が「見守る側」にとどまらず、同じ方向を向いて現場で共に動くことで、「自分たちは一緒に戦っている」という一体感が生まれます。
この“同志感覚”が、敬遠感を敬愛へと変える最大の要因になります。
こうした関わりが積み重なることで、部下は「この上司となら頑張れる」と感じ、上司自身も“支え合う関係”を実感するようになります。
それが、まさに「パートナー促進」段階の成功の証です。