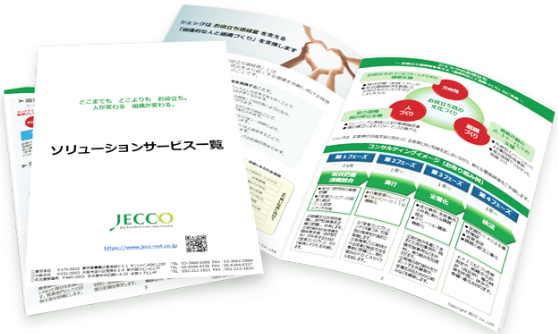組織文化の“見える化”をアクションへ ─人材開発と関係性改革で組織を動かす
~現場が動き出すための3つのステップ~
組織文化診断によって、「うちの組織は協調性は高いけれど挑戦が少ない」
「お役立ちの意識はあるけれど、上下関係に気を遣いすぎて意見が出にくい」といった、これまで“感覚的”だった組織の姿が、具体的な言葉とデータで見えてきます。
しかし、「見える化した」だけでは、組織は変わりません。
真に変革を進めるためには、診断で明らかになった課題を“行動の変化”につなげる打ち手が必要です。
今回は、「人材開発」「リレーションシップ改革」「行動定着支援」の3つのステップをご紹介します。
STEP1:「人を育てる」=行動変革の入口をつくる
たとえば、組織文化診断で「挑戦性が低い」と分かった組織であれば、単に「もっと挑戦しよう」と声をかけるだけでは、行動は変わりません。
背景には、「失敗を責められる空気がある」「自分のアイデアが通らないと諦めている」などの、これまでの経験で根付いた、上司や職場に対する固定観念が新たな行動のブレーキになっている場合があります。
そこで必要なのは、安全に一歩を踏み出せる“成功体験”の場を意図的に設計することです。例としては次のような設計を行います。
小さな挑戦を積み重ねるワークショップ(発想・実行・振り返り)
他者のフィードバックを通じて「変化に気づく」セッション
日常業務に直結した“実践宿題”とフォロー
単なる知識提供で終わらせず、「まずはやってみる」「自分の考え方と行動に気づく」「職場での実践で成功体験を積み重ねる」という一連の行動変革の流れを組み込むことが、成果を生み出す鍵です。
STEP2:「関係を変える」=リレーションシップ改革で空気を動かす
個人がいくら変わろうとしても、職場の空気が変わらなければ、元に戻ってしまいます。
だからこそ、組織文化の“土壌”にあたる関係性の質を高めることが、変革の土台になります。
たとえば、次のようなアプローチを取り入れます。
マネジャーと部下の1on1の質を高める(問いかけ、傾聴、承認)
部門間の“貢献と期待”を対話する場を設け、相互理解と協働関係を築く
組織文化診断の結果を「共通言語」として対話の出発点にする
ポイントは、「人と人の間にある“見えない壁”」を言語化し、信頼・共創を育む関係へリフレームすること。
このような関係性の変化は、風土そのものを動かす力になります。
STEP3:「続けられる仕組み」=現場に根づく行動支援
変革が一時的なものに終わってしまう組織には、共通点があります。
それは、「行動の変化」を支え続ける仕組みがないということです。
そこで、以下のような「定着支援」が重要となります。
上司が部下の行動変容を観察し、対話でフィードバックできるようになる
チームで月1回「風土と行動」に関する対話の時間を持つ(定例化)
外部支援者(ジェック)による定期フォローや職場訪問によって、「やりっぱなし」にならない運営を支援する
行動を「習慣」に変えるには、“繰り返し”と“支え合い”が必要です。
変化を起こす人を孤立させない仕組みづくりこそが、文化変革の持続力になります。
組織は、「人」と「関係」が変わると、動き出す
組織文化診断は、いわば“組織の鏡”です。
鏡に映った姿を見て、自分たちの課題や強みに気づいたなら、次にすべきは「行動を変えること」、そして「その行動を支え合う関係を築くこと」です。
ジェックは、現場に寄り添い、行動と関係の両面から、変革の実行と定着までを支援しています。