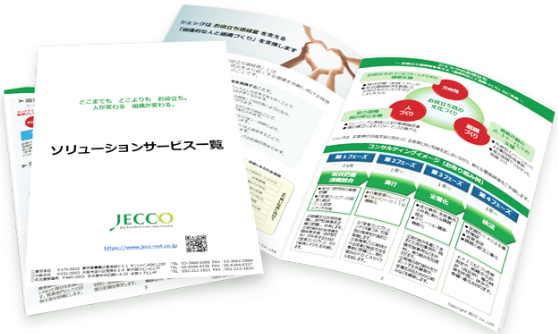組織は「脆さ」を克服できるか? BANI時代のレジリエント経営 ―「しなやかに立ち直る組織」へ
現代の企業経営において、変化への迅速な対応とレジリエンスの強化は不可欠です。本記事では、「VUCA」に代わる新しい概念「BANI」に焦点を当て、特に「脆さ」に注目します。複雑化と予測不能な出来事に対処するためには、従来の強さに頼るだけでは不十分です。「脆さ」が実際にどのように企業を危機にさらすのか、新たな挑戦にどう備えるべきかを解説します。
新たな時代を示すフレームワーク「BANI」
「VUCA」を超えて、「BANI」という言葉を耳にする方も増えてきたのではないでしょうか。Brittle(脆い)・Anxious(不安な)・Nonlinear(非線形な)・Incomprehensible(不可解な)という4つの要素を通じて、今の世界の「不安定すぎる現実」を捉えようとするのがこのBANIフレームです。
「Brittle(脆さ)」への注目
注目したいのは「脆さ(Brittle)」です。
BANIのフレームワークが注目される理由の一つは、従来の「強さ=安定」という発想ではもはや、複雑化・加速化する社会に対応しきれないことが明らかになってきたからです。
特に「Brittle(脆さ) 」は、頑丈さと柔軟性を取り違えた結果、予兆に気づかず、一点で急激に崩壊する組織や制度の特性を示しています。
「脆さ」の具体例 大手自動車メーカーの稼働停止
たとえば、2023年に発生したある大手自動車メーカーの国内工場の稼働停止は、わずかなシステムの不具合が全拠点に波及した典型例です。サプライチェーンの最適化や生産効率を極限まで高めた結果、いざというときの「ゆとり」や「クッション」がなくなり、トラブル発生時に回復できる余地が残されていなかったのです。
「見かけは堅牢、しかし脆い」システムの特徴
BANIにおける「Brittle(脆い)」とは、まさにこうした状態を指します。見た目は強そうに見えても、実は一つのきっかけで簡単に崩れてしまうような危うさをはらんでいます。システムに「融通がきく余白」や「バッファ(ゆとり)」がないと、ちょっとしたミスや想定外の出来事が、組織全体の機能不全につながりやすくなってしまいます。
だからこそ、組織の「脆さ」に目を向け、その構造的リスクに備える視点が今、必要とされています。
では、どうすれば企業や組織は「強そうに見えて脆い」から、「しなやかで折れない強さ」つまり「レジリエンス(Resilience)」を備えられるでしょうか。
「堅牢な組織」が崩れるとき
Brittleとは、見かけは堅牢でも、ある一点を超えると脆く崩れてしまう性質を指します。
たとえば、硬いガラスのように、一定の力までは耐えられても、それを超えると一瞬で粉々になる。そのような特性を持つ構造は、現代の企業やチームの中にも存在します。
「これまで成功してきたやり方」への過信
次のような状態は、一見うまく機能しているように見えますが、突発的な変化やトラブルに直面したとき、急速に瓦解することがあります。
・形式だけが残り、実質的な議論や意思決定が行われない定例会議(議題は毎回似通っていて誰も異議を唱えず、結論も形だけで現場に反映されない状態など
・「何かあっても誰かがなんとかしてくれるだろう」という無責任な楽観
脆さの根底にあるのは「行動理論」の硬直
私たちは、組織の脆さの原因の一つに「行動理論の硬直」があると考えています。ここでいう「行動理論」とは、これまでの経験を通じて心に刻まれた「自分なりの信念」(ジェック独自の概念)で、その人の考え方の前提となるものです。
たとえば、「何事もマニュアル通りにやるべきだ」「本音を言うと面倒なことになる」「失敗すると評価が下がる」などの信念は、仕事の精度を一定に保つ反面、変化への対応や内発的な創造性を妨げ、結果として「脆さ」を生み出してしまいます。
脆さに対抗するレジリエンスの鍵は「集団性格」
「集団性格(※1 )」とは、「挑戦」「協調」「お役立ち」の3つの価値観と行動様式で表す組織文化です。その組織に浸透している“当たり前”の価値観と行動様式がどのような組織文化であるかが重要になってきます。
この3つの軸はレジリエンスに大きく影響します。
・挑戦:変化を恐れず、新しい方法を模索する姿勢
・協調:互いの強みを活かし合い、柔軟に連携する関係性
・お役立ち:組織の外と未来に向けた価値創造の志向
この3つの軸が弱まっていると、ちょっとした外圧で動揺し、硬直し、やがて崩れていきます。
逆に、この3つの軸が高まっている組織は、一度崩れても立ち直る、逆境から学ぶなど、「しなやかな強さ=レジリエンス」を備えることができるのです。
「脆い組織」を「しなやかな組織」に変えるには
私たちが現場支援で実践している方法の一つに、「勢いづくりの五原則(※2)」があります。
これは、「お役立ち道の文化」─すなわちレジリエンスの源となる文化づくりに向け、組織全体を動かしていくための行動指針となるものです。
勢いづくりの五原則
■共通目的・共通目標の統合: 組織の存在意義と目指す目標を全員で確認・共有し、行動の土台にする。
■コォ・イノベーターの育成: お役立ち道の文化づくりに貢献する意欲あるメンバーの強みを伸ばし、中心的な存在に育てる。 (コォ・イノベーターとは 集団性格革新の協力者)
■ディス・イノベーターの改善: お役立ち道の文化づくりを判断規準として、あきらめずに指導し、共通目的・共通目標の再統合を図る。(ディス・イノベーターとは集団性格革新の阻害者)
■「もっともだ」の雰囲気づくり: リーダー自身が模範を示し、組織文化に基づいた言動でメンバーからの信頼を得る。(「もっともだ」の雰囲気とはリーダーに対する信頼の雰囲気)
■罰ライン(Yライン)設定とチェック: 組織の信頼を保つ最低限の行動基準(Yライン)を設け、全員で実践し成果につなげる。
特に重要なのが、コォ・イノベーターの育成と、共通目的・共通目標の統合です。「この変革は、自分にとっても意味がある」と自覚できた人が一人、また一人と増えていくことで、変化は加速します。
レジリエント経営とは「理念実践×内発的な変容」
BANI時代において、組織の「脆さ」を克服するためには、単なるルール変更や制度の整備だけでは不十分です。
重要なのは、「私たちは何のために働くのか?」という理念と、「そのために自分はどう在りたいのか?」という内発的な問いかけです。
ジェックでは、行動理論の改革と集団性格の革新を通じて、お客様の「お役立ちに満ちたより良い社会づくり」を支援しています。
「あなたの組織は、しなやかに変化できていますか?」
今こそ、組織のレジリエンスを問い直すときです。
※補足一覧
※1:集団性格について
※2:勢いづくりの五原則/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド