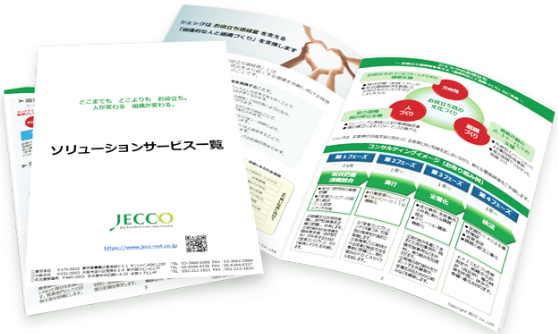マインドフルネスと行動理論─ウェルビーイングと「お役立ち」への実践的アプローチ
現代のビジネス環境は、BANI(脆い・不安・非線形・理解不能)の時代 に象徴されるように、急激な変化と不確実性に満ちています。先が読めず、複雑に絡み合う課題が山積するなかで、個人が心身の健康を保ち、組織が持続的に価値を創出していくためには、「内面の安定」を軸とした土台づくりが欠かせません。
その鍵となるのが「マインドフルネス」、そして、私たちが提唱する「お役立ち道経営」です。異なる言葉を使いつつも、目指す世界は重なっています。
マインドフルネスとは?
マインドフルネスとは、「今この瞬間」に意識を向け、評価や判断をせずに、自身の思考や感情、身体感覚に気づく状態を指します。瞑想や呼吸法を通じて実践され、ストレス軽減や感情の安定、集中力の向上といった科学的効果が多く報告されています。
実際に、GoogleやSAPといった先進企業では、マインドフルネス研修が導入され、社員の創造性やエンゲージメント向上に寄与しています。これは単なるメンタルヘルスケアにとどまらず、「自己を観察し、より望ましい行動を選択する力」を養う土台ともいえるでしょう。
「お役立ち道経営」の接点
ジェックが提唱する「お役立ち道経営」は、人間の根源的な動機である「誰かの役に立ちたい」という欲求に光を当て、それを支える経営のあり方です。
そこでは、「挑戦」「協調」「お役立ち」という3つの価値観と、それに基づく行動様式が組織文化に深く根づくことが重視されます。
〈3つの価値観〉
・挑戦:あらゆる可能性にチャレンジし続けようとする価値観
・協調:共創し、協働しようとする価値観
・お役立ち:市場や社会のお役に立とうとする価値観
※組織の一人ひとりが、社会の役に立つことを真に使命として、一致団結して、お役立ちにつながる新たな価値創造に向けて挑戦している組織文化を「お役立ち道の文化」としています。社会に選ばれ続ける持続可能な組織文化と言えます。
私たちはこのような組織文化を「集団性格」と呼び、社員一人ひとりが自らの「行動理論」に気づき、それをよりよく改革していくことで、全体の集団性格にも変化が生まれると考えています。
「行動理論」とは、これまでの経験を通じて心に刻まれた「自分なりの信念」(ジェック独自の概念)です。マインドフルネスの実践は、そうした信念への気づきを促し、より柔軟な選択肢を持つことへと導いてくれます。まさに「自己革新」の起点です。
3つの価値観とマインドフルネスの関係
「挑戦」「協調」「お役立ち」という3つの価値観と、マインドフルネスの関係を見ていきましょう。
1.挑戦:思い込みを手放し、可能性を拓く
マインドフルネスは、「こうあるべき」「失敗してはならない」といった固定観念に気づかせてくれます。これは、自分の行動理論を見直す第一歩です。内面を整理することで、新しい視点や選択肢が自然と生まれます。
2.協調:深い傾聴と共感の力
「相手の話に耳を傾け、心から理解しようとする」姿勢は、チームにおける信頼の基盤です。マインドフルネスは、感情にとらわれず「今ここ」に集中する力を育て、丁寧な対話を可能にします。
3.お役立ち:自分の行動が社会に及ぼす影響を意識する
「お役立ち」という価値観は、単に相手に喜ばれることではなく、自分の仕事が市場や社会にどう貢献しているかを見つめる姿勢です。ジェックでは、これを価値創造の主体として、社会のお役に立とうとする志として大切にしています。
マインドフルネスの実践は、この「お役立ち」の感覚を深める手助けになります。自分の言動が誰にどう影響しているかを静かに見つめることで、他者や社会とのつながりの中での「自分らしさ」が浮かび上がってきます。
それは「お役立ちイメージ」の形成につながります。お役立ちイメージとは、自分らしい役立ち方を言語化・可視化したものです。マインドフルネスはその内省のプロセスを支え、主体的な貢献意識を育てていきます。
マインドフルネスの実践のヒント
マインドフルネスの実践は、特別な道具や時間を必要としません。たとえば、以下のような簡単な取り組みから始めてみるのはいかがでしょうか。
・毎朝2分、目を閉じて呼吸だけに集中する
・会議前に30秒、全員で深呼吸する
・日々の「ありがとう」を、心から伝えてみる
こうした小さな習慣が、自らの行動理論への気づきを促し、周囲との関係性を育み、組織文化(集団性格)にも変化をもたらしていきます。
「最近、仕事が忙しくて心の余裕がない」と感じることはありませんか? あるいは「もっと意味のある仕事がしたい」と思うことはないでしょうか?
マインドフルネスとお役立ち道経営は、一見異なるアプローチでありながら、「自分を整える」「相手とつながる」という実践を通じて、結果的に「社会に貢献する」姿勢を育むという点で、共通の志向を持っているといえます。
この3つの循環(自己とのつながり、他者とのつながり、社会とのつながり)は、組織のウェルビーイングを高め、持続的な成長の礎となるでしょう。
まずは今日、静かに深呼吸から始めてみませんか。