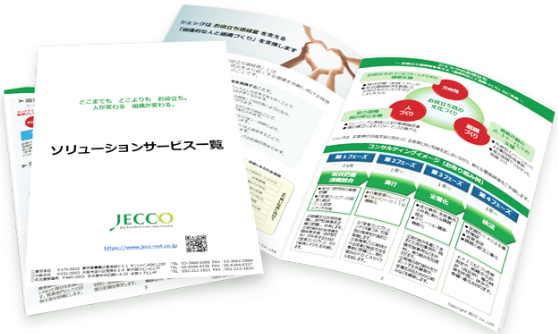評価面談を“納得感と成長の場”に変える─人事部門ができる支援の仕組み
1. なぜ今“評価コミュニケーション”が重要か
半期や年度末の評価面談は、社員にとっても組織にとっても非常に大きな意味を持ちます。
ただし現場からは「評価が一方的に伝えられて終わる」「マネジャーによって伝え方に差があり、不公平感がある」といった声が上がりやすいのも、この時期の特徴です。
評価の伝え方ひとつで、社員の納得感や次の成長意欲は大きく変わります。だからこそ、人事部門が積極的に支援し、評価面談を「結果通知の場」から「成長を共に描く場」へと変えていくことが重要です。
2. 現場で起きている課題
評価が「点数やランクを知らせる場」で終わってしまい、社員の行動変化や成長に結びついていない。
マネジャーごとに伝え方のスキル差が大きく、社員側の受け止めにムラが生じている。
リモートやハイブリッド勤務が進み、観察や日常対話の不足から納得感が得にくい。
これらの課題を、マネジャー個人の努力だけに委ねるのは限界があります。人事部門が「仕組み」として支援を提供することが不可欠です。
3. 人事部門ができる3つの支援策
(1) 「評価の伝え方」の型を提供する
評価面談の基本構造を「成果の事実 → 強み → 改善点 → 次への期待」といった流れで整理し、マネジャーが迷わず使えるようにシート化することが効果的です。
さらに、フィードバックに使えるフレーズ集や、短時間で学べる動画教材を用意することで、マネジャー全体のスキル底上げにつながります。
(2) 「納得感のある対話」を促す仕掛け
本人に事前に「振り返りシート」や「自己評価の問い」を渡すと、面談が一方通行にならず、双方向対話が生まれます。
また、マネジャーに対しては「問いかけ例」を共有することで、深みのある会話を促進できます。加えて、評価理由の記録を必須化することで、組織全体として透明性を高めることも重要です。
(3) 「成長を促すフィードバック」の仕組み化
面談の最後に「次の半年の行動テーマ」を必ず一緒に設定する欄を設けると、評価を未来につなげられます。
さらに、システム上で面談後のフォローアップを促進し、四半期ごとに「小さなフィードバック」を行う仕組みを作れば、成長支援が一過性で終わらなくなります。
強みに基づいたフィードバックを推奨するガイドラインを作成するのも有効です。
4. すぐ導入できる仕組み例
事前シートの作成:※以下のような項目をシート化
< 成果の振り返り>
・この半年で最も誇れる成果は何ですか?
・具体的にどのような行動や工夫が成果につながったと思いますか?< 学びと課題>
・この半年で自分が成長したと感じる点は?
・うまくいかなかったこと、改善したいと思う点は?<今後の挑戦>
・次の半年で挑戦してみたいことは何ですか?
・その実現のために必要なサポートは何でしょうか?<キャリア・意欲>
・中長期的にどのようなキャリアを描いていますか?
・その実現に向けて、今の仕事でどう貢献していきたいですか?
・この半年で一番誇れる成果は?
・今後挑戦したいことは?
フィードバックフレーズ集の作成:「改善点」ではなく「次にこうすればもっと伸ばせる」という表現を推奨して作成。
<強みを伝えるフレーズ>
・「特に〇〇の場面での△△は、あなたの強みが発揮されていました」・「〇〇の成果は、チーム全体に良い影響を与えました」・「あなたの□□な姿勢は、他のメンバーにも刺激になっています」<改善点を前向きに伝えるフレーズ>・(NG)「ここができていない」→ (推奨)「次にこうすれば、さらに成果を伸ばせると思います」・(NG)「ミスが多い」→ (推奨)「確認の工夫を増やすと、もっと安定した結果が出せそうですね」・(NG)「もっと積極的に行動してほしい」→ (推奨)「あなたの意見をもう一歩前に出すと、チームに良い影響を与えられると思います」<期待を込めるフレーズ>・「次の半年で〇〇に挑戦してほしい」・「今回の経験を活かして、□□に取り組めるとさらに成長できる」・「この強みを伸ばしながら、新しい領域でも活躍できると期待しています」面談後フォローの仕掛けをつくる:3か月後に本人とマネジャーへ「行動テーマの進捗確認」リマインドを自動送信。
こうした小さな工夫の積み重ねが、評価面談の価値を大きく変えていきます。
5. 人事部門が果たす役割
評価面談を「マネジャー個人の力量」に委ねるのではなく、
仕組み・ツール・ルールによって支え、誰もが納得感と成長実感を得られる場にすることが、人事部門の重要な役割です。
この時期の人事のひと手間が、社員の信頼感や組織へのエンゲージメント、そして人材の定着と成長に直結します。
「評価を伝える」から「成長を描く」へ─今こそ、その仕組みづくりを進めていきましょう。