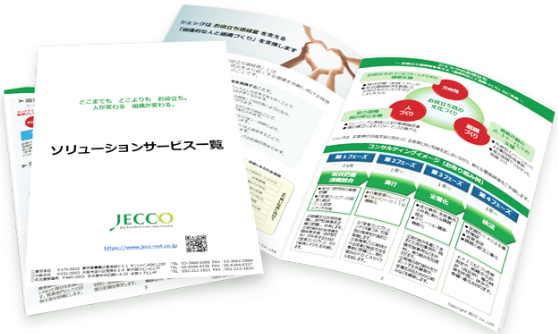ベテラン社員こそが「ミッション」の体現者に:次世代を導くためのマネジメントの再定義
若手社員の間では、企業のミッションや価値観に共感することが働きがいに直結しています。一方で、長年の経験を持つベテラン社員が、過去の成功体験や実績の延長で意思決定を行い、ミッションを“お題目”と捉えてしまうケースも少なくありません。ベテラン社員やマネジャーがミッションを軸としたマネジメントや後輩育成の規範となることの重要性と、その具体的な実践策について考えます。
なぜ今、ベテラン社員に「ミッション」が求められるのか
かつては業績や効率性を重視するマネジメントが主流でした。しかし、価値観が多様化し、若手が「意味」や「共感」を求める時代には、それだけでは人は動きません。
実際、多くの若手社員は「何のために働くのか」「誰のために役立つのか」といった問いに関心を持っています。そのとき、身近にいるベテラン社員が理念に背を向けていると、若手の“共感”が空回りしてしまうのです。
➤ミッションは、若手を動かすための“地図”であり、ベテランが見せる“行動”こそが“コンパス”になる。
ベテラン社員にありがちな3つの“ミッション誤解”
1.「理念より結果」:成果こそがすべてだという思い込み
→ 成果は大切ですが、理念と矛盾した成果は組織の信頼を損ないます。
2.「若手向けの話だろ」:自分はもう関係ないという距離感
→ 実際は若手が最も観察しているのは“ベテランの行動”です。
3.「ミッションなんて現場に関係ない」:理念は経営層の話という認識
→ むしろ現場でどう行動に落とし込むかが、ミッションの価値を決めます。
ミッションを“語る”のではなく“見せる”:実践のための3つの視点
1. 意思決定に理念のフィルターを通す
日々の判断において、「この選択は、我が社の理念と整合しているか?」を一度立ち止まって考えるクセをつけましょう。
たとえば、「短期的に数字は上がるが、顧客の信頼を損ねる」ような選択肢に対して、“理念に立ち戻る”ことができるかが分かれ目です。
➤実践ヒント:会議で「これは我々の理念と整合していますか?」という問いを投げかける。
2. 育成に理念を組み込む
後輩や若手への指導においても、単にノウハウや経験を伝えるだけでなく、「なぜこのやり方を選ぶのか」「この仕事の本質的な価値は何か」を言語化することが大切です。
それが理念とのつながりを自然に伝える機会になります。
➤実践ヒント:OJTで“技術”と一緒に“意味”を伝える。「この仕事は、何のためにあるか?」を一緒に考える。
3. 自らの言動が“理念の鏡”になるという自覚を持つ
自分がどう振る舞うかが、後輩たちの「企業観」や「職業観」に影響を与えます。
理念と一致しない言動(たとえば、社内の信頼を損なう発言や、他部署を軽視する態度)は、どんな言葉よりも強い逆効果となります。
➤実践ヒント:理念に反する“無意識の言動”に気づくために、他者フィードバックやチーム内対話を取り入れる。
ベテランが理念を“生きる”ことが、組織の文化を変える
企業文化は、制度やスローガンでつくられるものではなく、日々の行動の積み重ねから自然と形成されるものです。
特に、組織の“背骨”とも言えるベテラン社員の行動は、文化に大きな影響を与えます。なぜなら、若手社員は制度よりも「先輩がどう行動しているか」を見て、仕事の価値観や職場の常識を学んでいくからです。
「言っていること」より「やっていること」こそが文化をつくる
ベテランが理念を“語る”だけでなく、日々の意思決定、部下指導、関係構築、会議での発言、あるいは目の前の一つひとつの業務において、それを“行動”として体現している姿は、何より強いメッセージとなります。
たとえば──
・顧客との対応で困難な場面でも、誠実さを重視して判断した。
・部下の成果だけでなく、プロセスや姿勢を丁寧に認めた。
・社内の異なる意見に対しても、対話を通じて尊重した。
これらの行動一つひとつが、理念を「掲げるだけ」から「根づいた文化」へと変える礎になります。
また、ベテランが“理念を体現している”ことで、若手社員にとって理念が現実的で身近な存在となり、「この会社で自分も成長していける」という安心感と方向性を与えます。
理念が人の心に根づくと、ミッションに共鳴した人材が定着・活躍し、結果として組織全体のエンゲージメントや創造性も高まっていきます。
➤文化を変える第一歩は、「一番見られている人」が、一番理念に誠実であること。
まとめ
今、企業に求められているのは、過去の成功体験だけにとらわれず、未来に向けて“理念を軸とした判断”ができるベテラン社員の存在です。
「経験があるからこそ、理念を体現できる」という誇りと責任を持ち、次世代に“働く意味”を伝えていく姿勢こそが、これからのマネジメントのあり方と言えるでしょう。